世の中では、企業なるもの事業計画がなくてはならない、的話をよく聞きます。
私自身も、何冊かの本を買い込んで作ってみたことがありました。
けど、なんだかバカバカしくなってきたんです。
なぜなら、そこに書かれた数字に根拠が見えなかったからです。
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。
Contents
後継者に事業計画書は必要か?
アリバイ作り的事業計画書
なんだか事業計画書作ってまーす、なんていうとかっこいいですよね。
会社っぽくて。
実は、私もチャレンジしてみたことがあります。
そもそも、取引先のメーカーがつくれというから作った感じではあるのですが。
そのメーカーからフォーマットはもらったのですが、いまいちピンとこない。
数字をどれだけのばし、社員をどれだけ増やすっていう事にフォーカスされてるんです。
だから適当に、数字を入れていきます。
前年比〇%増収かな…
この辺で人増やして…
そのコストをどう賄うとか、全然触れられてないので、これに盲目的に従うとかなり危険だと思いました。
で、自分でも少し勉強してみたわけです。
何冊か、事業計画書の作り方、的な本を買ってみます。
その時に知ったのですが、世に出ている事業計画書の作り方の多くは、金融機関を納得させるためのものでした。
いかに融資を引き出すか?という目的ですね。
すこし割り切った言い方をすると、
「それなりにもっともらしくて、それなりに収益を上げそうで、論理的に納得感がある事業計画書」
というものを作り上げるのが目標のような気がします。
計画づくりの達成感
さて、計画づくりというのはなかなか達成感のあるものです。
実は、私が学生時代は、結構計画にはこだわりました。
というのも、中学生のころ、成績は5段階の1と2ばかり。
ときどき3が含まれる程度でした。
当時の担任から、
「あなた、このままだとあの〇〇高校ぐらいしか行けるところないよ。」
といわれてしまいました。
私の中学校時代は、校内暴力真っ盛りの時代でした。
その〇〇高校というのは、その中でもかなりデンジャラスな学校と聞いています。
命の危機を感じた私は、中学3年生の夏休みにかなり気合を入れて勉強しました。
なにより〇〇高校は男子校です。
あこがれていた、キラキラと輝く高校生活は、送れそうにありません。
この時に、テレビを見るのをやめ、ひたすら部屋にこもりました。
その時に作ったのが、夏休みの時間割と、勉強の進度の計画でした。
たっぷりと1日使って計画を立てました。
その時点で、かなり達成感があり、計画だけで終わりかけましたが、気を取り直し実行です。
月曜日の8時から英語、9時からは数学
8月10日までに数学の問題集はここまで終わらせ、
8月15日までに英単語を300個覚える・・・という感じですね。
で、何が起こったか、というと、1週間目からの挫折。
当初予定していた通りには勉強は進みません。
一方、勉強の進度にこだわるあまり、焦ってしまい、身についていない状態で次々と進んでいかざるを得なくなりました。
これでは本末転倒です。
そこで随時見直しをすることにしました。
ざっくりした進度の目標は持つものの、そこにはこだわりすぎない。
また、当初作った時間割で各教科に割く時間のウェイトも正しくなかったことが判明し、随時差し替えを行いました。
さらには、少し気分が乗らない食後などの時間は、簡単な計算問題や英単語、漢字学習の時間にするよう時間割を変更。
数学の難問を解く時間の後は、記憶問題など比較的頭の負荷の低そうなものをゴロゴロしながら教科書を読む。
そうやって、なんとなくパターンができ始めたのは、夏休みも半分終わったころです。
おかげで、中学3年の2学期以降の成績は、1と2は消え去り、3~5だけになりました。
なによりも、高校は共学のごく平均的な高校に進学することができたのは、私にとって大きな成功体験でした。
共学に進学することと、キラキラの高校生活は別物である、という現実も後程痛いほど知らされましたが・・・笑
計画は思い通りいかないもの
後継者の計画づくりには見直しのフェーズを
さて、ビジネスの話に戻りましょう。
中学生が高校受験という目標を達成するために作った計画でさえ、実効性のあるものができるまで何度もやりながらの変更が必要でした。
そして、その登場人物は自分一人でした。
これが、企業となれば複数の登場人物があり、周りを取り巻く変数は限りなく多い。
事業計画というものは、どれだけ作りこんでもその通りに事が運ぶ方が異常とさえいえるかもしれません。
金融機関に提出するのが目的なら、ある程度割り切って作ればいいでしょうが、現実に活かすつもりであれば常に見直しが必要という事です。
四半期に一度の見直し程度では、現実とのかい離があまりにも大きくなりすぎます。
結果より行動を定める
さらに注意したいことがあります。
高校受験の計画は「自分がやることを定めた」という事。
しかし、多くの事業計画書は、「結果」ばかりを重視していないでしょうか。
結果というのは、行動があってのものです。
単に金融機関提出用の割り切り事業計画ではなく、社内で生かそうとするならやはりこの行動、何をするかが大事でしょう。
「結果」はコントロールできないことが多いですが、「行動」ならコントロールできます。
たとえば、売り上げを今期10億にすると計画したとします。
何を、どれだけやれば10億円になるかが明確になっていなければ、単なる「できたらいいなぁ」という願望です。
そんな結果だけを書き記して、行動の内容はちゃっちゃで埋めてしまう内容だととにかくやれー!的な根性論で終わってしまいます。
だったら、初めから回り道などせずに、「今年の目標は10億円必達だ―!」と適当に決めてしまえばいいのです。
今日の教訓:さしあたっての必要性がなければ事業計画より行動計画
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。
メールマガジンのご登録

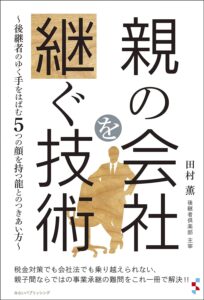













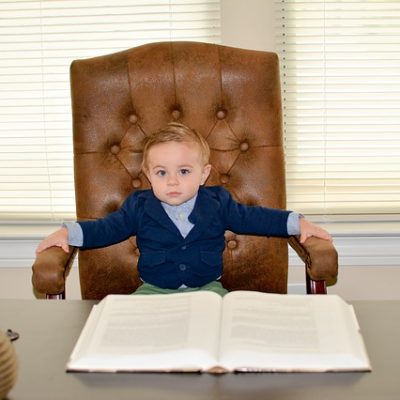






この記事へのコメントはありません。