「社長、大変です!」
慌てた様子でメッセージを送ってきた社員。
何事か?、と問い返すと彼女は答えます。
「間違ってました。・・・どうしましょう?」
大量に印刷した資料の一部に誤りがあった。
メッセージはその対応についての相談でした。
————————————————————
小冊子無料ダウンロードはコチラ
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

————————————————————
見てみると、「9日」と表記すべきところ、
「8日」となっています。
これ、ダイレクトメールです。
1000枚ほど印刷して、その間違いに気づいたわけです。
この問題に対して、はじめは
「どう間違いを隠そうか?」
ということを考えていました。
修正テープ?
同じ色の紙に正しい数字を印刷して切り貼りする?
うまく隠す?
いろんなアイデアが出ましたが、
はたと気づきました。
ご存知ですか?
ダイレクトメールでは、不安定な見栄えほど反応が高まる傾向があるということ。
たとえば、この数字、これ見よがしに二重線を引いて訂正する。
すると、人はそこに目が留まります。
結果、読まれる確率が高まるという考え方。
こぎれいなものより、手書きのDMのほうが反応がいいとか、
バランスの悪いDMのほうが反応がいいとか言われます。
書き込みのあるDMも、もちろん反応がいいとされています。
つまり、結果として、反応率がいい(かもしれない)DMが出来上がります。
このことを、単なるポジティブ・シンキングというつもりはありません。
私がこの”事件”から気づかされたのは、
ある意味において正しいことも、
ある意味においては誤りである、
ということです。
整理しましょう。
現実に起こったのは、ミスタイプという問題です。
これを、きれいに整ったレターをお客さんにお送りする、
という視点で見れば訂正するなど言語道断。
新たに印刷しなおすとか、見てわからない程度にうまく訂正するとか、
手間暇かけて体裁を整える必要があります。
しかし、単に効果を上げるDMという観点で見れば、
なかなかやろうと思わない、手書きでの書き込みという、
反応率を上げるテクニックを図らずともやらざるを得ない状況になった。
そんな風に見て取ることもできます。
最終的には、どちらの”目的”を採用するかです。
当然今回は、後者を選択しました。
私たちは、二元論的に物事を判断しがちです。
良いか悪いか、右か左か、正しいか誤りか。
こうなると、意見はぶつかり合い解決を見ない。
最終的には力で相手をねじ伏せようとする。
事業承継でも同じことが起こります。
先代が正しいか、
後継者が正しいか。
先代の意見を採用するか、
後継者の意見を採用するか。
こういった二元論で会社は揺れがちです。
しかし現実は、もう少し複雑です。
ある意味においては、先代が正しく、
別の意味においては、後継者が正しい。
そんなことが日常茶飯事に起こります。
それをどっちが正しい!?
なんていう議論にしてしまうから争いが絶えない。
私たちは、もう少し寛容であるべきじゃないか。
そんな風に思った出来事でした。
こだわりは大事ですが、
相手や、相手の意見を許すこと。
受け入れること。
そんな意識をするだけで、
どうにもならないかに見える関係が、
ほんの少し、緩むこともあるのではないか。
そんな風に感じました。
————————————————————
小冊子無料ダウンロードはコチラ
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

————————————————————
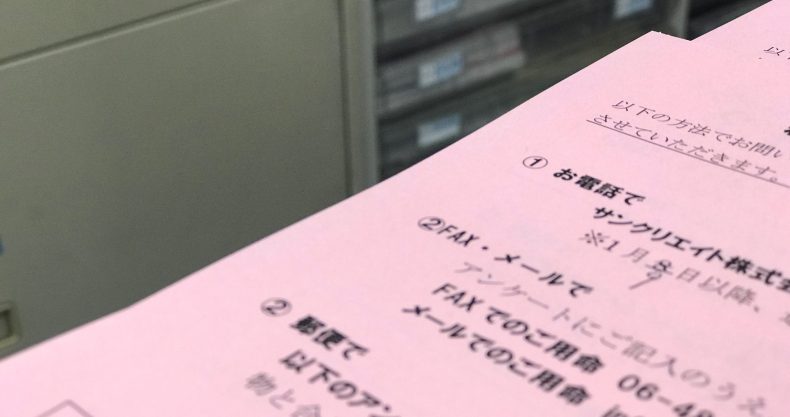
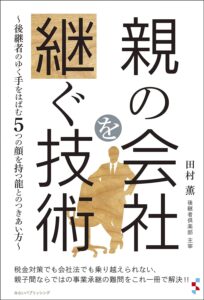
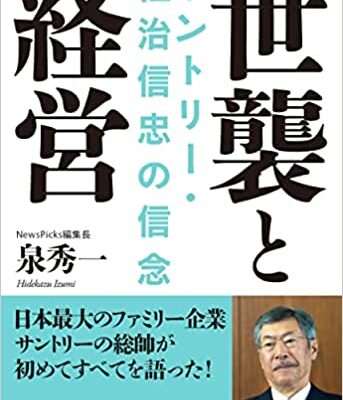



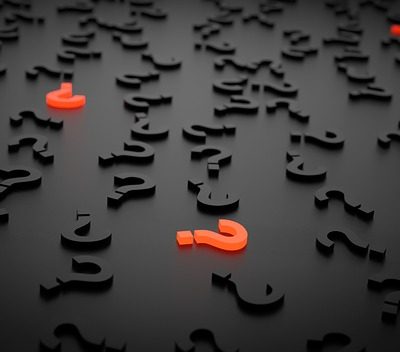
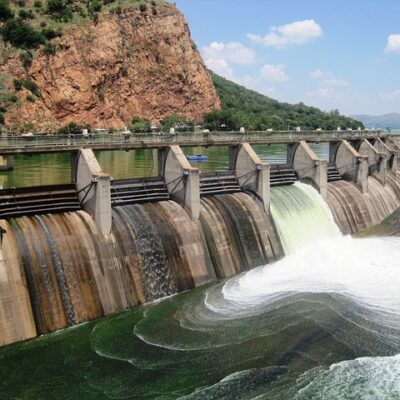





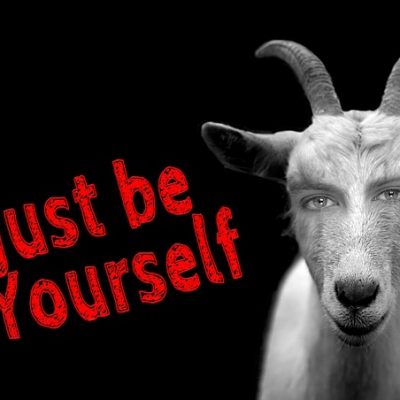
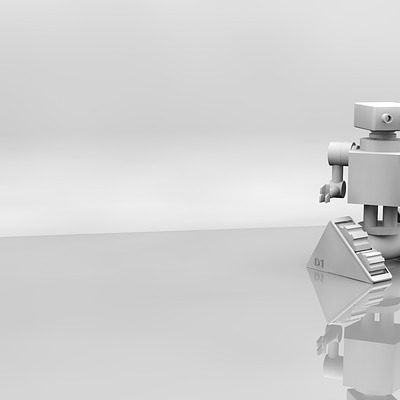







この記事へのコメントはありません。