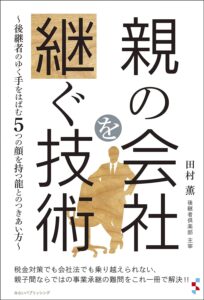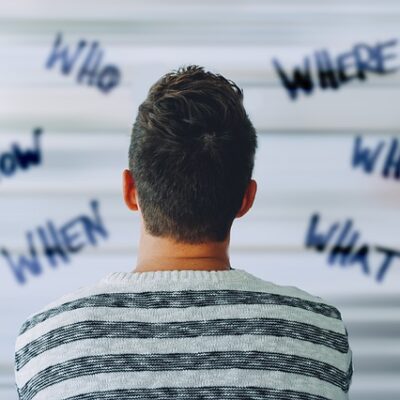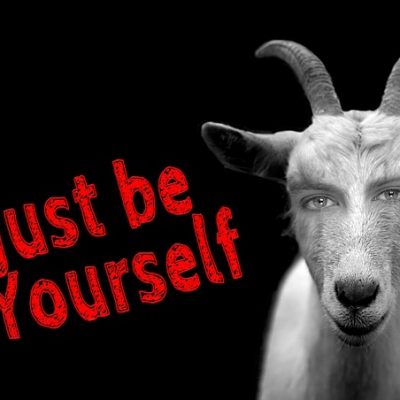色んな会社がいま、M&Aをしたりしています。
一昔前は、M&Aなんていうと大きな会社の大きな合併のイメージしかありませんでした。
しかし、今では小さな中小・零細企業でも結構盛んにM&Aが行われています。
私はその専門家ではありませんが、色々見聞きした話から感じた雑感をここでご案内したいと思います。
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

私と同じ保険代理店を売却した、というケースがまず思い浮かびます。
この仕事は、基本的に営業社員と顧客のつながりが基本的なビジネスの中心にあります。
だから、顧客開拓の手間を省くために、M&Aを行うというケースが多いように思います。
特に社長が高齢化している場合は、今の保険会社(メーカー)の要望に耐えられない(たとえばIT化や組織化など)。
だから、もうこの辺で一区切りついて、あとは人に任せよう、と。
とはいえ、後継者を育てたわけではないので、大きなところに買い取ってもらうというのがパターン。
この世界、営業がすべてなのですが、自分で自分の食い扶持を稼げる営業マンというのはほとんどいません。
だから、店主が社員を雇うために稼ぐといった構図があります。
そこで店主を欠いた買収を行うと、数年以内に数字は半減以下。
また、店主の年齢プラスマイナス10歳ぐらいが大方の顧客の年齢層。
高齢化店主には、高齢化した顧客層となりがちです。
そういったことを含めて、買い手は顧客開拓の一環として、同業他社を買い取ります。
顧客は人につくので、だいたいは消えてしまうので、あまり中長期のビジネス発展は見込みにくい。
ということで、割と刹那的な意図で変われるというか、取り急ぎの瞬間最大風速的な数字のために書いとる場合も多い。
一応、従業員も引き取る形をとりますが、数年でその人たちはいなくなるよう仕向けることが多いのではないかと思います。(ここまで見たわけではないですが)
他の業界においても、基本的には「販路」の一つとして買い取るケースが多いと思います。
ときおり、そこの許認可を得るためとか、製造ラインを手にするためとか、事業の存続が実現するケースもありますが、私の知る限り少数派に感じます。
技術を買うとか、色んなことがM&Aの背景にはあろうかと思います。
ただ、その社風なんかをずっと継続していくというのはあまり見かけません。
なんとなくですが、経済合理性をベースに行われるM&Aが多いように思います。
結局その決断をする頃、社長はビジネスへの意欲を失っている事が多いので、それも仕方のない事かもしれません。
ある小売店では、そのお店を買い取った業者は商品や設備を全部入れ替えて、倉庫のようにしてしまったと聞きました。
こうなると、M&Aというよりも、倉庫を買っただけ、みたいな話です。
こんなシーンを見ていると、M&Aで何かを残すというのは本当に難しい事なんだな、と感じます。
何が言いたいかというと、M&Aは本来の事業承継とはやっぱり本質的に別物だという事。
いろんな意味で、ここに幻想を抱かない前提で話を進めるのが良いのではないかと感じるのですがいかがでしょうか。
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。