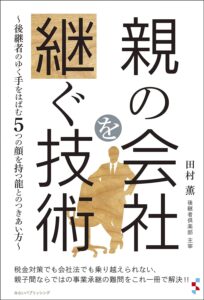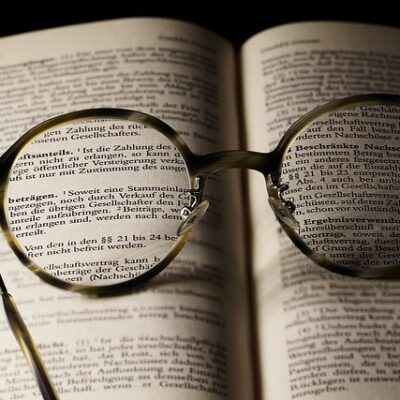そんなに勇気のいらない努力からは、それなりの結果。
けっこう勇気のいるチャレンジからは、けっこう大きな結果(良くも悪くも)がやってくる傾向があります。
事業承継で後継者がやることって、そこそこ勇気のいる決断を、必要なタイミングで行うことなのではないでしょうか。

私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。
事業承継で後継者が、なんの波風もたたない状態で親の会社を引き継げるか?というとまずそんなことはないと思います。
私たち後継者は
どれだけスムーズに、事を荒立てずに継承するか?
という事を考えがちです。
けどそれは基本的にはムリじゃないかと思います。
静かに継承しようとしても、社会情勢が変わりますから、売上がじりじり下がってきて、
最終的に、会社を締めるとかリストラするかとか、
M&Aするかとか、まあそんな判断が必要なシーンも出てくるでしょう。
自分で仕掛けなくても、何かしらのハードルは必ずやってきます。
待つだけのハードルは、たいてい、追い詰められるようなものです。
ストレスも激しいです。
だったら、前に進むような動きをして見たいと思うのですがいかがでしょう。
じゃあ、なぜ事業承継って穏やかじゃないのでしょうか。
たとえば、臓器移植って、「拒絶反応が怖い」と聞いたことがあると思います。
他人の臓器をいれると、身体は拒絶反応を起こして、その臓器をはじき出そうとします。
組織も同じです。
何かが外から入ると、組織はそのよそ者を外にはじき出そうと必死になります。
事業承継においては、「後継者」というよそ者、「後継者の考える会社像」というなじみのない部外者を一度ははじこうとする力が働きます。
これを医学の世界では免疫抑制剤なんかで、力づくで抑えようとするわけです。
実際は手っ取り早く、組織の免疫を押さえようとするのが事業承継あるあるです。
けど不思議なもので、押さえようとすれば、反発が起こります。
後継者が躍起になればなるほど、組織は後継者や後継者の考え方を拒みます。
これをどうすればいいかというと、
①従来の組織の味方であることを信じてもらう
②変化への小さな階段を作る
③変化に慣れてきてから後継者自身の意志を伝え始める
という流れが比較的スムーズじゃないかと思います。
ちょっと意識して見てください。

私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。