当社の社内の会議をリアルタイムでお届けしよう。
そんな恐ろしい企画も、第十弾。
さて、そろそろ実行フェーズに入ってきたので、
ここに書くことも少なくなってきました。
ちなみに、前回の記事はコチラです。
後継者が会社を変化させる全過程1【社内会議リアルタイム実況】(最初の記事)
後継者が会社を変化させる全過程9【社内会議リアルタイム実況】(前回の記事)
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

小冊子無料ダウンロードはコチラ
Fecebookページに「いいね!」をお願いします。
考え方から実行へ。
流れはそんな風に進んできました。
Contents
はじめの一歩
結局やってみなくてはわからない
この会議においては、小難しい話から入りました。
私たちはお客様にどんな価値が提供できるか?という問いです。
10回の会議を経て出た結論は、
日ごろ使っていない会議室をレンタルスペースとして開放しよう
というアウトプット。
経緯のわからない人からすれば、なんのこっちゃ?
という感じですね。
正直、私自身も不安です(笑)
ただ、軸として「地域の方々との交流を」というベースは守られています。
高齢者をターゲットにしよう、という話はいまやほぼ消えています。
実は、それはそれでいいと思っています。
当初ターゲットを定めたものの、上手くいく方法が見つからなかった。
ではほかのターゲットではどうか?
そしてそれが上手くいったとき、本来のターゲットに応用できないかを考える。
実際のところ、戦略というのは頭で組み上げる段階と、実行段階では動きが変わることがあるのかもしれません。
実行計画において、初めて自社のリソースの有無に気付く。
SWOT分析もいいけど、ターゲットとそこへの働きかけを
何度も何度も考え直すと、実行段階でリソースや強みに触れざるを得ない。
だから重要なのは、誰に、何を提供するかを考え続ける事ではないかと思っています。
レンタルスペース
さて、空いてる会議室を貸す。
これだけでは、戦略(流れ)としては、ぶつ切りです。
そもそも空いてる会議室を貸して、その人たちとどうコミュニケーションをとるのか。
彼らが当社とどのように絡んでいただけるのか。
全くの未知数。
社内からも、当社のイベントとして主催しなければ意味がないのでは?
という意見もありました。
しかし、当社としては集客という行動、未経験です。
これを経験するのはいい機会。
そしてどんな形であれ、それを名簿にすることが当面のミッション。
こういった方々との薄いつながりを少しずつ濃くしていく事を考えていくのが次のステップでしょう。
ということで、ゆるーく始まります。
レンタルスペースの集客が。
マーケティングという考え方
社員が成長する機会
今回の会議に際して、既にマーケティング担当より、
●レンタルスペースに関する規定
●レンタルスペース事業における個人情報保護における同意書&申込書
●サービス告知用のチラシ
●看板
が準備されています。
基本的にはいつでもスタートできる状況になりました。
実際には、盆明けからの稼働となりますが、ここで地域住民のニーズが探ることができそうです。
実は、マーケティング担当が予想以上に大活躍です。
「以前の看板では、この記述はすごく見てくれていた。多くは高齢の女性」
「この告知で問い合わせされることをもとに、次のサービスを作っていけばいいのでは?」
「お客さまはここまで動いてくれるから、あともう一歩踏み出すのにこうすれば?」
とりあえずできた看板は、内容としては粗削りなぶぶんはありますが、あえて口は出さないことにしました。
なぜなら、マーケティング担当者はお客さまの反応から自分で学ぶことができる事がわかったからです。
次回以降、彼女の報告を会議で行ってもらうことで、社員全員の意識の底上げができそうです。
セミナー開催のオファー
私もそこに弾みをつけたいとおもっていると、ある企画のオファーを頂きました。
これはすでにペットとしての猫の老後や、猫の保護などを行っているNPO法人の主宰者のかた。
近日、ご自身の本を出版されるという事で、ぜひ当社を使わせてほしい、という話です。
その他にも、自分の教室を試しに開いてみたい。
そんな人とコラボ出来ればいい、その時にベビーシッターをお願いしておけるシステムにしたい、
まぁいろんな意見があるわけです。
ここに来れば、場所と情報がある。
そんな地域の情報拠点としての価値が地元でできてくると、面白そうです。
もう一度基本に立ち返って
時々不安になるのです。
この会議に意味はあるのか。
当社のビジネスは、これでよくなるのか、と。
しかし、ここで過去の投稿を見直して思う事があります。
当社のミッションの一つに、この世の中から保険の必要性をなくすこと、を掲げています。
その方法の一つは、人と人が繋がる事です。
ターゲットを高齢者にしたり、子育てママにしたり、軸がぶれまくっているようで不安だったのです。
しかし、相手がだれであれ地域のつながりを作り出すことができれば、それは世の中に価値を提供しています。
その拠点として当社が機能するとすれば、それは必ずビジネスとしても成立するはずです。
暫くはそれがお金にならない期間もあるでしょうが、一つずつ形を作っていく事で、あるべき姿になるような気がしてきた・・・
といえばあまりに甘すぎるでしょうか。
難しいのは当たり前。
私たちは新しい業種分類を作ろうとしているのですから。
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。


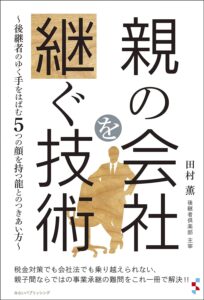












この記事へのコメントはありません。