同族会社の二代目社長は、会社に新しい風を起こそうとします。
そこには大きく二つの流れがあるかと思います。
一つは商品やサービスの拡充。
もう一つは販売や製造の自動化。
いずれの場合でも、外注化や業務提携というのは選択肢として有効でしょう。
ただ、この外注化を前提としたビジネスモデルには危うい部分がある事は含んでおいたほうが良いでしょう。
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

■小冊子『なぜ親子経営では確執がおこるのか?~そのメカニズムを知り、後継者が”今”を打開するための5つのステップ[要約版]』無料ダウンロードはコチラ
■YouTubeチャンネルで動画配信も行っています!こちらをご覧ください。
ある企業で、リーズ(見込み客)獲得を外注化したところがありました。
外注業者がWEBサイトを作り、広告を出し、その商品に関心のあるお客さんが外注業者に問い合わせメールを送る。
その問い合わせ情報を、その企業が買い取る。
また、顧客層が似ている別の事業を営む経営者仲間と組んで、共同で集客を行う。
いずれも、比較的楽にビジネスを加速させる手段として有効だと思います。
ただ、こういったスキームが上手くいきはじめると、一気にその売り上げに依存する可能性はあります。
自社でコツコツ売るよりも、簡単に大量に売れてしまう。
この時点では「成功例」として取り上げられるのでまあいい気になってしまいます。
売上は一気に上がり、周囲は羨望の目で見る。
売上に応じた生産体制を整えるため、将来への投資をバンバンしていく。
一見、成功者に見えるのですが、常に頭に置いておいた方がいい事があります。
その成果は、その会社の販売力からもたらされたものではない、という事です。
これは非常に危うい状態で、リーズ獲得の外注会社がリーズの提供を断ったとしたら、提携先があなたとのビジネスを停止したとしたら、
将来への投資はそこで不良債権となってしまうかもしれません。
何が言いたいかというと、自分の販売力を持たないという事は、非常に危ういところにいる事を常に認識しておく必要がある、という事です。
結局は、顧客リストを集める力を持つ業者が強くなります。
結果として、下請け企業となってしまう事があるわけです。
だからといって、提携や販売の外注をやるな、と言っているわけではありません。
一時的なやり方としては非常に有効ですから、どんどんやるべきだと思います。
しかし、最後の落としどころとして、すべて内製化すべしとは思いませんが、外注業者は常に交換可能な状態を保ちたいものです。
自分の会社の経営の根幹は、自分で握るべきであり、外からのコントロールに出来るだけ左右されないよう考える事が重要かと思います。
すぐにできる事ではないかもしれませんが、外注化で時間稼ぎをし、その間に外注業者に頼らない仕組みを作る。
外注業者との距離感としては、それぐらいがちょうどいいのではないかと思います。
外注を活用するのは大事ですが、外注に依存しないよう注意が必要なのではないでしょうか。
【後継者の社交場】
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

■小冊子『なぜ親子経営では確執がおこるのか?~そのメカニズムを知り、後継者が”今”を打開するための5つのステップ[要約版]』無料ダウンロードはコチラ
■YouTubeチャンネルで動画配信も行っています!こちらをご覧ください。

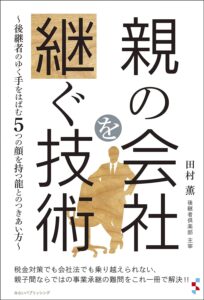

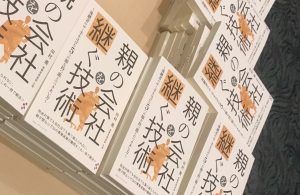
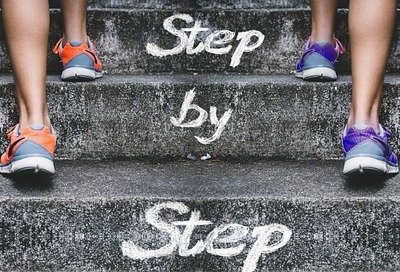




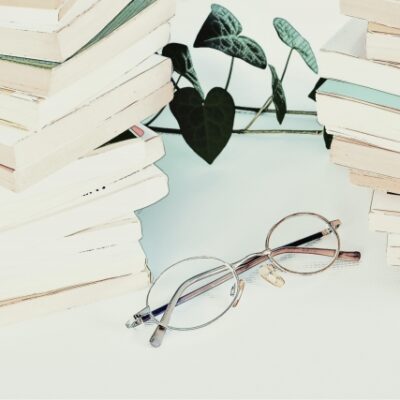





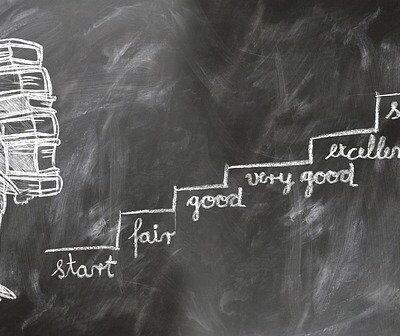







この記事へのコメントはありません。