事業承継に終わりはあるのでしょうか。
一つの区切りは、先代の完全な引退でしょう。
多くの場合、そのタイミングは都度引き延ばされ、いつまでたっても状況は変わらない。
そんな時、後継者の立場として、どう対処できるのでしょうか。
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

「65歳になったら引退する。」
多くの創業社長が口にする言葉です。
その時点で、創業社長が65歳の自分をしっかりイメージできているかは不明ですが、一つの区切りとしてそんな年齢が認識されているようです。
ところで、後継者であるあなたが学生時代、スポーツをやっていたとしましょう。
そこでコーチに言われるわけです。
「トラック100周!」
息も絶え絶えになりながら、ランニングを続けます。
汗が噴き出し、単調なトラックを砂煙をあげながら走り続ける。
あと、10周、あと5周、あと3周。
終わりが見え始めると、だんだんと力が復活してきます。
もつれそうな足を引きずっていたのが、このあたりから足取りもしっかりし始めます。
あと10m、5m・・・ゴール!
達成感を味わいながら、地面に倒れこむ。
耳の奥に、自分の心臓が早いリズムを刻むのを聞きながら、無心で空を見上げる。
そんな時に耳に入ったのは、コーチの声。
「よーし、じゃああと50周だ!」
一気に、達成感は消え失せ、失望のどん底に落とされる・・・。
人は、期間を限定されると意外と頑張ることができるものです。
多少の困難も、「あと1週間の我慢」「あと100m走れば」「あと100問の問題を解けば」と、終わりが見えると無理がききます。
しかし、一方で終わりのない苦行は、実際の苦しみ以上に心をむしばみます。
事業承継というイベントが、例えば3年限定などといった一過性のものであれば、ここまで思い悩むことはないでしょう。
もうすぐ先代は65歳だとすれば、宣言していた通りであれば、自分の代がやっと来る。
そう思っていると、たいていその期間は引き伸ばされます。
しかも、その理由は、後継者であるあなたが「頼りない」から、という理由で。
「まだまだ代は譲れん。わしは70歳まで頑張るからその間に何とかしろ」
それは、だんだんと伸びていきます。
そして大抵は、先代が体調を崩すまで続きます。
私の場合もそうでした。
父は、当初65歳で引退すると公言していました。
それは次第に伸びる一方、ある時期、リウマチで体調を崩しました。
その期間は、休み休みの出勤でした。
もうワシもそろそろ完全に引退するぞ、なんていうので私もそれなりの覚悟をするわけです。
が、それが快方に向かうと今度は生涯現役を主張し始めました。
周囲のものはてんやわんやです。
皮肉な話ですが、先代が体調不良になると事業承継がすすみ、体調が戻ると社内も元に戻る。
ある企業ではこんなことがありました。
やはり社長(先代)が体調不良で、1か月も入院することになりました。
社内では、先代に心配をかけまい、と基本的に先代への情報をシャットアウト。
その代わり、日々の報告書をご子息である専務がまとめて行うことにしたそうです。
これまで、社内で大きな存在感のあった先代がいなくなることで、会社が一致団結した好例です。
社員は、ご子息を中心にまとまり、私はこういったのを覚えています。
「事業承継、完了しましたね」と。
しかし、退院後、数か月で先代は戦線に復帰。
結局、先代の入院前と同じ状態に戻ってしまったという事です。
振出しに戻ったわけです。
ご子息と社員は顔を見合わせていたことを昨日のように覚えています。
さて、終わりが見えないのはきつい。
これはスポーツや宿題だけではありません。
事業承継の中で、継続的なストレスがある以上、これもまた終わりのない苦行です。
ここで終わり、という宣言をされては延ばされ、延々とトラックを走らされているような状態です。
誰も、親を親が作った会社から追い出したいなんて思いません。
しかし、永遠に続くかのような苦しみから逃れようと、後継者はそんな行動に駆り立てられるのです。
そう考えて、先代を追い出しにかかるとこれまた大変なことがおこります。
大企業等でもよく起こるお家騒動は、大抵はこんな形で起こることが多いのではないかと推測しています。
後継者がここまで追いつめられるのは、
①時間がない(社内改革が世の中の変化に間に合わない)
②自由がない(自分の裁量で動かせる物事が少ない)
③立つ瀬がない(そもそも会社を潰せば二代目の責任となる)
といった三つの「ない」が影響しているのではないかと思います。
ただ、もう一つの選択肢として、
耳を貸さない
というのもアリじゃないかと思っています。
65歳でやめる、75歳でやめる。
そんな事を言っても、
「ふーん」
です。
期待もしないし、耳も貸さない。
生涯現役だといっても、やはり
「ふーん」
です。
こんな様子だと、親はカリカリ来ます。
もちろん、先代は一人で焦ったり、一人で怒ったりすることもあります。
それも含めて耳を貸しません。
私は私の道を歩む。
それだけです。
状況を無理にコントロールすることも考え、試した時期はありましたが、縛ろうとすれば抵抗は大きくなる。
だから、好きにすれば?という考え方に変えました。
どうせ聞かないんですから。
終わらない苦しみの兆しを感じ始めたら、苦しみを苦しまない方法を考えればいい。
そんなシンプルな考え方です。
もちろん、横で先代がおこりだすと後継者である自分の心もざわつきます。
しかし、それも慣れると、平然と見過ごすことができるようになります。
親に従わなければならない、という子供の思い込みから抜け出すいいトレーニングではないかと思います。
じゃあ、歯ぎしりしてる親をどうするかって?
親の感情に責任を持てるのは、少なくともわたしたちではないはずです。
親自身が折り合いをつけていく必要があるのです。
同族企業の事業承継は、親と子が成長するためのステージなのですから。
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。


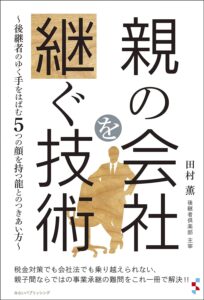

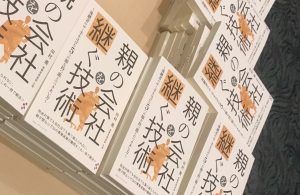













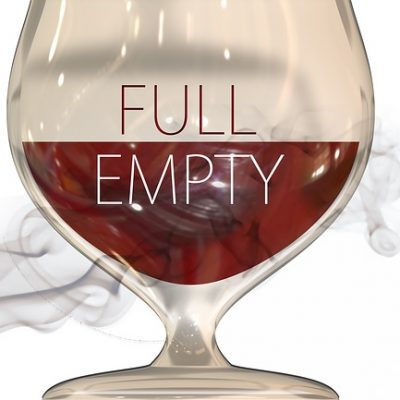






この記事へのコメントはありません。