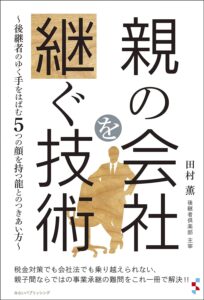一時期、AIの発達で、10年後にはこんな仕事がなくなる、なんていう話が喧伝されました。
オックスフォード大学の試算でも、2015年時点で、仕事の約半分はAIで代替できるという話もありました。
しかし現実はどうかというと、AIはとても発達してるし、人がいなくなった職場も無いわけではない。
ただ、完全にはそうはなっていないという事。
世の中が変わるには、時間が必要なのです。
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。

まれに、コロナパンデミックの時のように、ある日を境に環境が一変することはあります。
ただ、多くの場合は、ビジネスというのはゆっくりと変化していくもの。
たとえば、私のいた保険業界などは1990年代から業界は変わる替わると言われ続けていました。
そこから30年余りたって、確かに変わったこともあるけど、変わっていないこともある。
正直なところ、1990年代のビジネスモデルとほぼ変わらない形で、ビジネスは続けてこられていると言えます。
マスコミや業界関係者は、あたかも世の中が一瞬にして変わるかのように喧伝しますが、現実はそうではないのです。
たとえば、冒頭であげたAIに及ぼされる影響を考えてみましょう。
10年で半分の仕事がなくなると言いながら、AI失業という話はあまり耳にしません。
かつて、世界中に工業化が進んだとき、農家は工場で働くようになりました。
その流れは、思った以上に自然な流れだったような気がします。
なんだかんだいって、時代に順応する時間はそこそこあることが殆ど。
後継者は、そんな時代の変化に一刻も早く対応しなければ、と焦りがち。
焦ることそのものは悪い事ではないと思います。
けどそこで、組織のスピードと自分の思いのギャップのずれがあると、組織は疲弊しがちです。
後継者としては、自分のスピードについて来いよ、と思うわけですが、そう都合よく組織が動くわけではありません。
行列の先頭に立った後継者は、時々、後ろを振り返って、社員がついているかを気を付けてください。
そして、社員に声をかけたり、フォローしたり、教育したりして、足並みをそろえるように意識してください。
いくら後継者が一人焦っても、会社はまとまることはありません。
だから、一刻も早く進みたい気持ちは抑えつつ、みんなのペースを見ながら歩みを進めてください。
そうすることではじめて、組織の力を引き出すことができるようになります。
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。