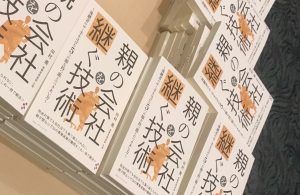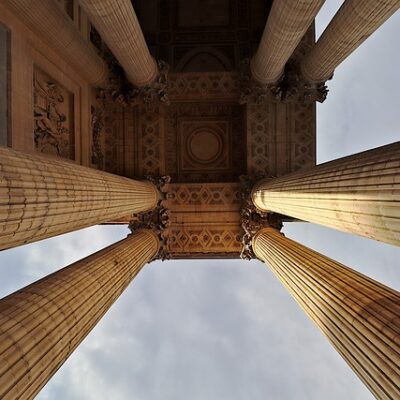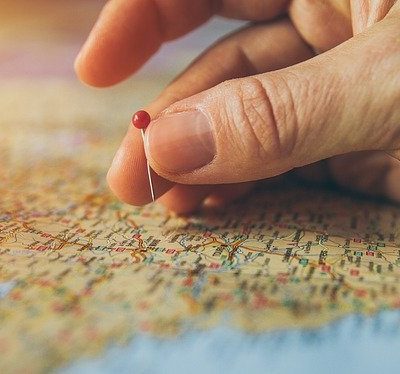家業を持つ社長を親に持った子供。
なんとなく宿命のように、後継者として一緒に働きだす。
しかし、働きだすと親子の仲は悪くなる。
こうやって要約するとシュールな展開ですが、
その原因の一つは双方がもつ価値観です。
じつはその価値観は、似ていないようで似ている可能性が高いようです。
詳しくは、続きをご覧ください。
——————————————
後継者向けセミナー開催日程はこちら

小冊子『なぜ親子経営では確執がおこるのか?~そのメカニズムを知り、後継者が”今”を打開するための5つのステップ[要約版]』無料ダウンロードはコチラ
YouTubeチャンネルで動画配信も行っています!こちらをご覧ください。
Contents
親子関係の盲点
親子関係における二つのタイプ
たまたま本を読んでいたら、面白い一文に出合いました。
それは、こんな感じの内容でした。
親子関係には二つのタイプがある。
一つは、親の価値観をまねて生きる子ども。
もう一つは、親の価値観に反発するけど、親に似る子ども。
思わずずっこけました(苦笑)
その本では、親子の価値観が似ることからは避けられない、と締めくくっています。
その文に目を留めたのは、自分にも思い当たる節があったからかもしれません。
気づかなかった「親似」の自分
私はどちらかと言えば、後者のタイプ。
親の価値観にはとことん反発しました。
それが明確になったのは、親の会社に入社し、専務となった頃でしょうか。
親は何でもかんでも自分で決めてしまう。
事前に相談もなければ、まるで自分が決めたものにはすべて従うべきとでもいうかのように、私のスケジュールまで決めてしまう。
たとえば、あるお客様への同行訪問に際して。
来客のアポイントに際して。
私の都合を聞かず、勝手に決めてしまいます。
決算での利益処分なんかもそう。
もっと有意義な使い方を、と思っていても勝手に決めて(私の価値観からすれば)しょうもないものを買う。
勘弁してくれよ、と思って自分はそうなるまい、と思ってたんです。
しかししかし、妻は私が父に言う言葉と同じことを私に言ってきます。
「勝手に決めないでよ」と。
「孤立」を知らず知らずのうちに作り上げる後継者
初めのうちは、妻の言葉は無視してました。
けど、だんだんと自分でもわかってくるんですね。
自分がやられたらいやなことを、他人にやっていることが。
たとえば、会社の戦略。
これからの会社はこうあるべきだ、と勝手に自分で思い込む。
それ自体は悪いことではないと思います。
しかし問題は、自分のうぬぼれにありました。
自分は先代はおろかほかの社員より経営について勉強している。
だから、俺のいうことをみんな聞くべきなんだ、と。
こうやって言葉にすると、恥ずかしいぐらい自己中心的です。
ああ、自分は親の価値観に反発してたにもかかわらず、親に似たんだな・・・
と思った次第です。
他の人間からしてみれば、先代である親はそれなりの実績を残してきた。
だからある程度のワンマン経営は、アリだと考えるでしょう。
しかし、実績のない私が同じことをすると、やっぱり総スカンを食らっても仕方がない。
「自分は孤立してる」と嘆いている自分が、実はそういう環境を作り上げていたことにやっと気づいたわけです。
他人を受け入れるという感覚
「みんなバカ」と思っていた(かった)私
すごく失礼な話なんですが、私は一時期自分は他人より優れている、と思っていました。
と言っても、基本はあんまり自分に自信がないほうなんですが、自分が頑張ってる分野ではスゴイと。
自分ほど頑張ってるやつはほかにいないはずだ。
まあそんな感じで、周囲を排除してました。
人の意見を聞かず、「いやいや自分の意見が正しい」と言い張る。
ひどいときには、せっかく意見をくれた人に対して、どれだけ自説が正しく、その人の意見が間違ってるかを論破する。
乱暴な表現をすれば、こいつらバカじゃないの?と思ってたわけです。
少し表現が極端に聞こえるかもしれませんが、そうやって他人に勝てそうな部分だけでも勝てる自分でありたかったのでしょう。
自分を一気にレベルアップさせる方法が見つからない以上、相手を見下すことで何とかアイデンテティを保っていたのかもしれません。
そういえば、これもよく妻に言われてました。
「いつも上から目線でものをいう」・・・と(苦笑)
他人は鏡である
よく言われる話ですが、ムカつく相手のムカつく態度は、たいてい自分がやっているものです。
たとえば、自慢話ばかりするアイツがうざいとすれば、自分も無意識にやっている。
しかも、自慢話をしている自分が、どこか嫌なんです。
そんな自分の嫌な部分を他人に見出すと、たまらなく腹立たしい。
冒頭の話にあったように、子どもは親の価値観をトレースします。
自分の持つ価値観に嫌悪感を持っていると、当然それを持っている親にムカつくことになります。
親のことがどうしても受け入れられない、ということがあるとすれば、それは親の問題でもある一方で、自分の問題でもあるわけです。
逆に言うと、自分の中にあるイヤな部分を克服できれば、親のそんな態度に平然と接することが可能になります。
自分が変わるという選択
自分に対して何かしらのネガティブな思いを持っていると、周囲をコントロールしようとしがちです。
自分以外のヒトやモノが、自分の思う通り動くことで、自分の存在意義を実感するためです。
それは、親自身がそうであったりもしますし、後継者自身もそういった価値観を受け継いでいます。
もちろん、価値観を受け継いでると言っても遺伝ではありません。
育成環境が強く影響を及ぼしている、という意味です。
遺伝でなければ、変えることは可能です。
実は親子経営での問題の1つは、相手を変えようという考えを親子双方が譲らないことにある、と私は考えています。
自分が正しいから、相手は誤りである。
だから自分に従うべきだ、というのが親子での確執の根本的な原因ではないでしょうか。
そうした時に、延々と相手を変えようと手を緩めないのが、親子の確執です。
しかし現実に目を向ければ、相手を変えるよりむしろ自分を変える事のほうが手っ取り早い。
しかも、そのためにはゆとりが必要になります。
この議論を譲っても、自分の価値は下がるわけではない、という自尊心。
私はそれを人間としての「ゆとり」だと思っています。
こだわりは意固地と仲がいい
意固地でいるより楽
たとえば、会社の戦略を社員といっしょに考えようとしたとします。
たいていは稚拙なものであることがほとんどです。
何しろそういう視点を持つという習慣がなかったから。
そういった人たちをガイドし、人として成長させるのが管理職の役割の一つだと思います。
そして、そういう稚拙な戦略は、当事者は失敗して初めて稚拙さに気づくものです。
ここでも管理者は失敗に寛容でなければならないわけです。
その対象は、一般社員だけでなく、先代に対しても、です。
自分のやり方にこだわるのは、失敗が許せないという後継者のもつ価値観に原因があると思います。
失敗はすなわち、自分の価値を貶める行為、と信じているからそうなると思っています。
しかしそれは意固地になるのと紙一重です。
私はずいぶん長い事、意固地でい続けましたが、そこを少し脱した時、意固地でいるより受け入れたほうが楽だな、と感じ始めました。
なぜなら、自分が何事においても社内で一番でい続ける必要がなくなったからです。
ここでも出てくる親譲りの価値観
いやいや、そんなこと許せない。
絶対に譲れない価値観は守り抜くぞ。
会社にはぶれない軸が必要なんだ!
と力説したくなる気持ちもわかります。
ぶれない軸は確かに大事だとは思います。
けどそこにこだわり続けるのは、やっぱり親譲りの価値観じゃないでしょうか。
俺の会社だから、俺流でなければならないってやつですね。
私が気に入らなかった先代の価値観の押しつけを、私が社内でやっていた、と自分で気づいたときはちょっとショックでした。
今までも気づいてはいたけど見ないようにしてたんです。
やってることは似ていても、ニュアンスが違うんだとか、やり方が違うんだ、とか自分に言い訳しながら・・・
それをもうどうでもいいや!ってなると、割と自由なんですよ。
もちろん、一生懸命やらないっていうことではなくって、ちゃんとみんなの価値観を受け入れようと考えただけです。
それだけで、自分にとっての会社の存在感がずいぶん変わったんです。
こだわりを捨てたら自由になれた
そんな変なこだわりを捨て始めると、いい意味で会社がどんな風になってもいいように思えます。
上手くいくか行かないかはともかくとして、誰に何と言われても、自分がそれなりに楽しめる経営できたらいいかな、と。
それ以来、ちょっと気持ちにゆとりができたような気がします。
これを無責任という人もいるかもしれませんが、気にしません。
たしかに、売り上げがさがってるとか、社内がざわざわしてるとか、気になる事はいっぱいあると思います。
けど焦ったところで状況は変わらないし、むしろ大変な時ほど落ち着かなきゃ、と思うわけです。
ある程度の神経のずぶとさは必要ですが、みんなおんなじ苦労して立派な経営者になってるわけです。
まあ、慌てず騒がず、淡々とやるべきことをやっていくのが、いいんじゃないかと思います。
慌てて繰り出した戦略なんて、たいていうまくいかないものだし。
今自分たちは、我慢することを、我慢せずに済む方法を学んでる最中なのかもしれません。
我慢は体に毒なので、これまで我慢と感じていたことが我慢にならない心のゆとりをもてるよう意識していくのが大事なのだと思います。
こだわりを捨てるコツ
これはあくまで、私が意識した方法です。
もし使えそうなら、参考にしてみてください。
まず、たとえば親に対してだったり、社員に対して「怒り」の感情が出てきた時、気を付けて自分の内面を観察します。
怒りというのは第二感情と言われているそうです。
要は、何かがあったから怒る・・・というわけではないそうです。
何かがあって、そこに対して何かしらの感情を感じて、その感情の回復のために怒りをあらわにするようです。
たとえば、自分の出した意見がおざなりにされて、怒りを感じたとします。
それは、意見がおざなりにされたことに怒りを感じているのではない。
意見がおざなりにされたということは、自分のことが重要視されなかった悲しさや寂しさに結びつけている背景があるようです。
だから、自分が大事にされる状態を作るため、怒りを表現して他人の注目を浴びたり、怒りによって相手を下げることで自分の立場を保つといった傾向があるようなのです。
するとその怒りの裏には、おざなりにされた、と感じている自分がいます。
そういう自分を、つどつど説得するんです。
これは自分をおざなりにしたのではなくて、単に意見が受け入れられなかっただけだよ、と。
そもそも意見を否定されたら自分を否定されたと考えるのは思考の習慣です。
逆に言えば、習慣を改めればいいのですから、根気よく自分を説得するというのが手っ取り早い方法です。
アタマの思考回路を書き換える感じですね。
ある日突然変化する・・・というわけではありませんが、着実に変わっていくのが自分でもわかると思います。
似た第三者を見ることでわかることもある
こういった自分のことは、なかなか見えない。
オヤジにそっくりと言ったって、たいていの人は真っ向から否定されます。
よりによって、自分は違うぞ、と。
そういったことは自分だと見えにくいから、他人の様子を見て知ることが可能になります。
似た境遇の人のふるまいを見ればわかるのです。
そこで、似た境遇の人たち・・・つまり後継者が集まる場所、ということです。
私自身様々な後継者の集まりに参加してきましたが、やっぱり結構似てます(笑)
それを単に他人事として見ていると気づきにくいのですが、自分に置き換えてみるともしかしたら・・・と思うこともけっこうあります。
そうやってお互いの身だしなみチェックではありませんが、お互いのふるまいをチェックしあう場所として位置付けると参考になる事もあるかもしれませんね。
——————————————
後継者向けセミナー開催日程はこちら

小冊子『なぜ親子経営では確執がおこるのか?~そのメカニズムを知り、後継者が”今”を打開するための5つのステップ[要約版]』無料ダウンロードはコチラ
YouTubeチャンネルで動画配信も行っています!こちらをご覧ください。
田村の日常
変な夢を見ました。
夢の中で私は自室で寝ていて、隣のベットでは変なおっさんが寝ています。
彼は白髪交じりの髪を長く伸ばした浮浪者風の男。
実はその人は、小山昇さんという方。
ビジネス書を読む方なら、小山昇さんの名前を知っている人も多いと思います。
経営品質賞を二度受賞した株式会社武蔵野を率いる名物社長。
その人と同じ部屋で寝ていて、勝手に家の中をうろつくのです。
なんだかいろいろ部屋を見られるのは嫌だなぁと思いながら、何かしら彼にアドバイスを求める自分。
その内容を忘れるという「一番大事なこと」を聞き漏らした形で目が覚めました。
うーーん、なんとも惜しい話です。