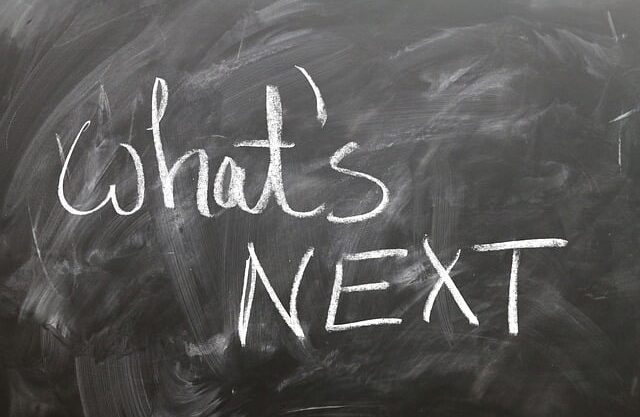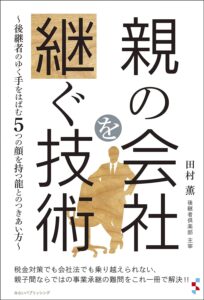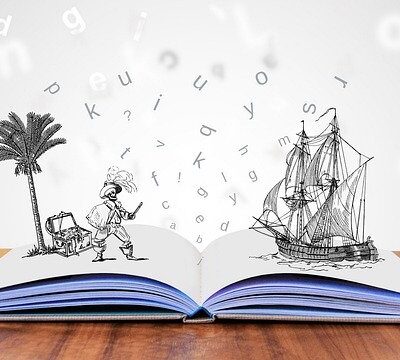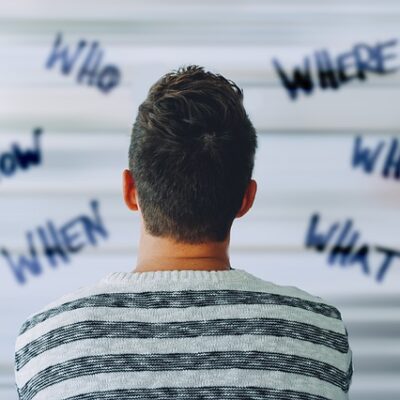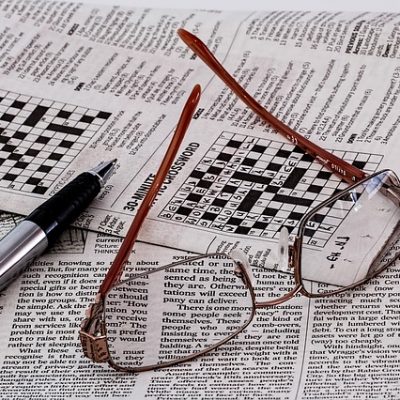後継者が親の会社位はいると、色んなフェーズでいろんなことを考えると思います。
ただ恐らく、あるタイミングまでは、「安定した会社にしたい」という思いが強くなるんじゃないかと思います。
しかし、会社の安定を目指すと、組織が不安定になる、というジレンマが発生することがあります。
それはどういったものなのでしょうか?
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。
Contents
後継者が会社の安定を目指すときに行うこと
後継者はルールや管理がお好き?
会社の安定を目指すと、何が起こるのでしょうか。
これは、会社の安定を目指したときに行う施策のデメリットを見ていくとわかりやすいと思います。
安定は、仕組み化でもたらされます。
仕組み化はとても大事なのですが、仕組みを維持するにはけっこうな力が必要です。
その力が大きくなりすぎると、社内に非効率を生み、硬直化を生みます。
中小企業なのに、大企業病に陥ってしまうのです。
具体的には、仕組みを動かすルールに縛られ、柔軟性が失われて行きます。
「安定」は例外を認めないこと。
それはすなわち、組織の硬直化を生み出すのです。
大事なのはバランス
だからと言って仕組み化がダメというわけではないのです。
仕組み化に対して、キッチリと管理する部分と、ゆるさを保つ部分のメリハリをつければいいだけです。
しかし特に、仕組み化の始まりは定着するまでは大変。
ついつい口うるさくなりがちです。
その時点でしっかり作りこむのはいいとしても、どこで緩めるかなどの判断は難しいところ。
結局、ガチガチのままにしてしまうと、組織はだんだんモチベーションを失っていきます。
後継者は組織の硬直化にどう対応すべきか?
後継者は「問い続ける」
一度硬直した組織は、なかなか柔軟性を取り戻すのは難しい。
そこに至る道は、心理的安全性にあるのではないか、と私は思うのです。
仕組み化は管理と近い部分にあります。
その管理は必要とはいえ、遊びの部分が必要なのではないかと思います。
たとえば、リッツカールトンで有名なのは、顧客に喜んでもらうためには一定の予算を現場の裁量で使えるという事。
たしか30万円くらいだったかと思いますが、現場社員が勝手にそのお金を一組の顧客のために使えるのです。
中小企業でそこまでするのは難しいかもしれませんが、裁量を現場に委ねるというのは一つのやり方です。
それは、いきなり独自判断させることをしなくても、会議などで「意見を聞いて、それを採用する」という形でもよいと思います。
後継者は決めることに固執しなくてもいい
経営者の仕事は「決める」ことだとよく言われます。
しかし、いつまでも自分で決めていれば、社員の自律性は養われません。
社員に決めることを任せるという事も、後継者の役割だと思います。
つらいところは、責任は自分が持たなければならない所です。
だからさすがに100%反対なことは、反対すればいいと思うのですが、どうだろう?と思うことならやらせてみるのも一考です。
後継者は常に問う
後継者としては、自分が引っ張っていくようなリーダーシップを目指しがちです。
しかし、それで失敗する後継者が多いのも事実。
ならば、常に社員に問いかけるスタイルのマネジメントを採用するのは如何かと思います。
会社を変えたいなら、毎日こう問うてください。
「皆さんが仕事をしている中で、どんなに小さなことでもいいので何か改善点を思いついたら教えてください」
3日に1件でもアイデアが出てくればしめたものです。
それを検討することで、その社員も経営に参加することになります。
そうやって社員の自主性も育まれていくはずです。
私の著書です。
関心を持っていただいた方は、画像をクリック。