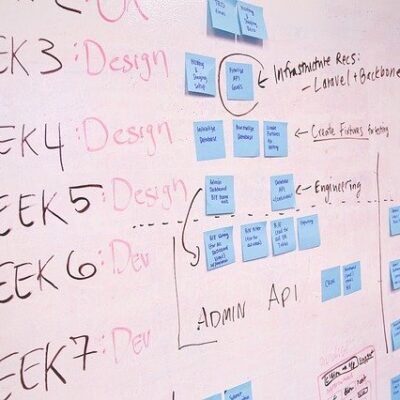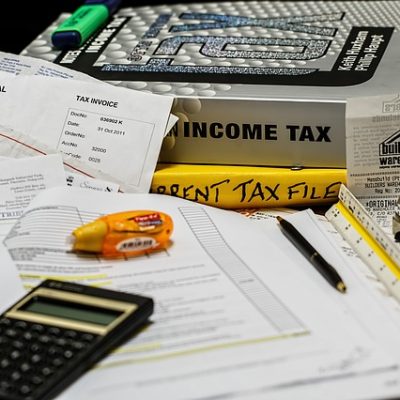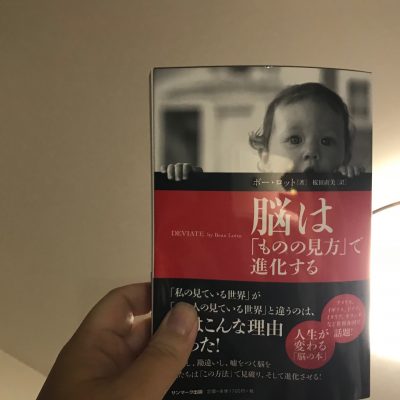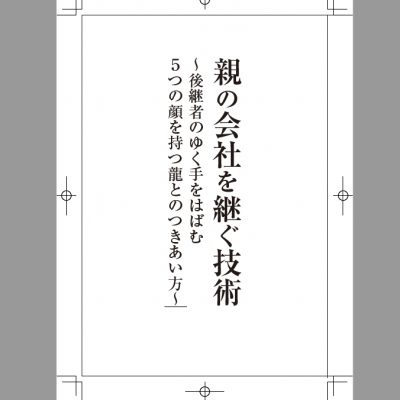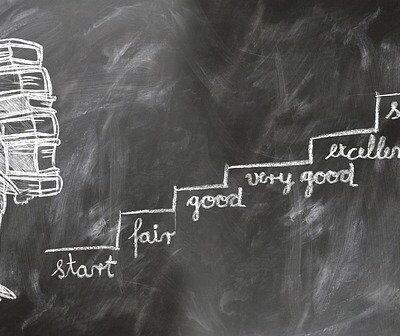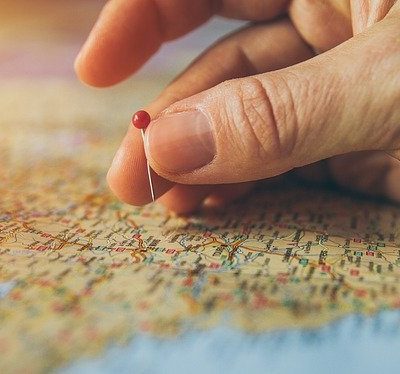後継者・跡継ぎ・二代目社長というのは社員とのコミュニケーションに迷うことも多いと思います。
社員の大多数は自分が採用した人でもなければ、自分より先輩であることも多い。
こう言ったときに人をまとめていくのに、どうすればいいのでしょうか。
私たちの親の時代というのは、昭和的な努力と根性の時代だったと思います。
当時は努力は報われる可能性が高かったので、そこに向かって頑張ればとりあえず大きな間違いはなかったようです。
だから誰よりも努力することが正義で、後継者・跡継ぎ・二代目社長は、その中でもトップに立ち、「一番頑張っている人」の座を根性で奪い取る必要があったかもしれません。
しかしそれは昭和的価値観の世界。
今の世で、努力と根性だ!なんていって、残業が増えたり、朝から晩までお客様の迷惑を考えない営業したりするのはもはやパワハラや犯罪と言われてもおかしくない世論があります。
昭和時代の正義はいまでは犯罪です。
この昭和時代のマネジメントを「働きかけるマネジメント」とひとまず言います。
どういうことかというと、「やれ!やれ!」と自分のみならず社員にも、何かの行動をせよという働きかけを行うマネジメント。
一方で、今の時代はたとえば、「売上を無理にあげないで利益を出す」「週休三日で経営を成り立たせる」「会社へは出社しないでも会社が回る」ということが正義になりつつあります。
こう言った状態に持っていくには、直線的な力技としての努力というより、ちゃんと考えて効率の良い行動や仕組みが必要になってきます。
脳みそまで筋肉ではなかなか難しい時代です。
それはすなわち、一人一人が全ての力を発揮して事業を作っていくことが大事です。
そのためには、押さえつけたり、後ろから背中を押すというより、自らやってみようという気持ちを育てることが必要となります。
自ら動きたくなるためには、リーダーは彼らを受け入れ、安全な場所をつくらなければ彼らは冒険をしません。
そんな冒険できる環境をつくるのが、近年のマネジメントと言われているのではないでしょうか。
とにかく社員の自主性を重んじるマネジメントです。
後継者・跡継ぎ・二代目社長であるみなさんがどちらをとるかは自由です。
ただ、親である先代がやっているからと、昭和的マネジメントを踏襲する必要はまったくありません。
それをするためには、古参社員をごぼう抜きしてトップに立たなければなりません。
しかし、受け入れ型のマネジメントであれば、自分がトップでなくとも、そこにいる人が働きやすく、自分の能力を最大限発揮できる環境をつくればいいのです。
だから、新人であっても可能です。
そういった受入れる力と、上手く巻き込む力をつけていくという事を意識すると、自然なリーダーシップが取れる可能性もあるのではないでしょうか。